お疲れさまです。今日も一日頑張ったあなたへ。
今夜の晩酌のおともに「NISA」と「福祉制度」の話でもどうですか?
え、難しそう?いやいや、今回は“素人でも分かる”ように、超ざっくり&ゆるく解説していきます。
そして、この記事を書いている私は社会福祉士であり、子育て中の父でもあります。
制度を「使う側」の目線でも、現場で「支援する側」の目線でも、しっかり語っていきます。
NISAってそもそも何?
簡単にいうと「税金がかからない投資口座」
NISA(ニーサ)は、少額からの投資を応援するための制度で、ざっくり言えば…
- 利益に税金がかからない(普通は20.315%の税金が引かれる)
- 2024年から新NISAに移行して、もっと使いやすくなった
- 積立投資も一括投資もOK!
- 誰でも使える(18歳以上)
お金を“預けて増やす”時代から、“自分で動かして増やす”時代に変わってきています。
福祉制度とNISAって関係あるの?
実は関係あるんです。
福祉の世界では「生活保護」「年金」「障害年金」などの収入・資産の状況が大事になります。
そしてここがポイント:
NISA口座の資産は、原則「資産」としてカウントされます。
たとえば、生活保護を申請するときや、高額療養費の対象になるかどうか判断するとき、
NISAに入れてる資産がチェックされることもあるのです。
でも、逆にいうと――
- 子どもの将来の教育資金
- 将来、年金だけでは不安な老後資金
こういった将来的な不安をカバーする意味では、NISAも立派な“福祉的な備え”とも言えます。
子育て世帯にとってのNISA活用
我が家にも1人、まだ小さな子どもがいます。
将来のことを考えると、正直不安もあります。
教育資金、食費、医療費、住宅費…
福祉制度はあるけれど、「十分」とは言いがたい。
だからこそ、今できる備えを少しずつでもやっておきたい。
NISAはそんな「将来の自衛手段」として、考える価値があると思っています。
よくある疑問:NISAと福祉制度、どっちを優先すべき?
これ、難しい問題ですが…
【答え】まずは福祉制度の活用。そのうえでNISAを検討。
生活がカツカツなら、無理にNISAを始める必要はありません。
まずは使える福祉制度をフル活用することが先です。
具体的には:
- 児童手当・就学援助
- 医療費助成制度
- 住宅確保給付金
- 地域の子育て支援センター活用
- ひとり親支援、障害福祉サービス など
それでも余力があるなら、NISAで将来への備えを始めてみてもいいでしょう。
まとめ:制度は使いこなしてナンボ!
NISAも福祉制度も、
知っているかどうか、使えるかどうかで人生が大きく変わります。
そして、私はその両方を“自分ごと”として見ています。
社会福祉士として、そして親として。
だからこそ、こうして晩酌しながら語れるような形で、
制度を「身近」にしていきたいんです。
今日の一杯が、あなたの未来の備えにつながるきっかけになりますように。
【おまけ】役立つリンク(外部サイト)
- 金融庁:新NISAの概要
NISAを知る:NISA特設ウェブサイト:金融庁 - 全国の福祉制度検索
介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

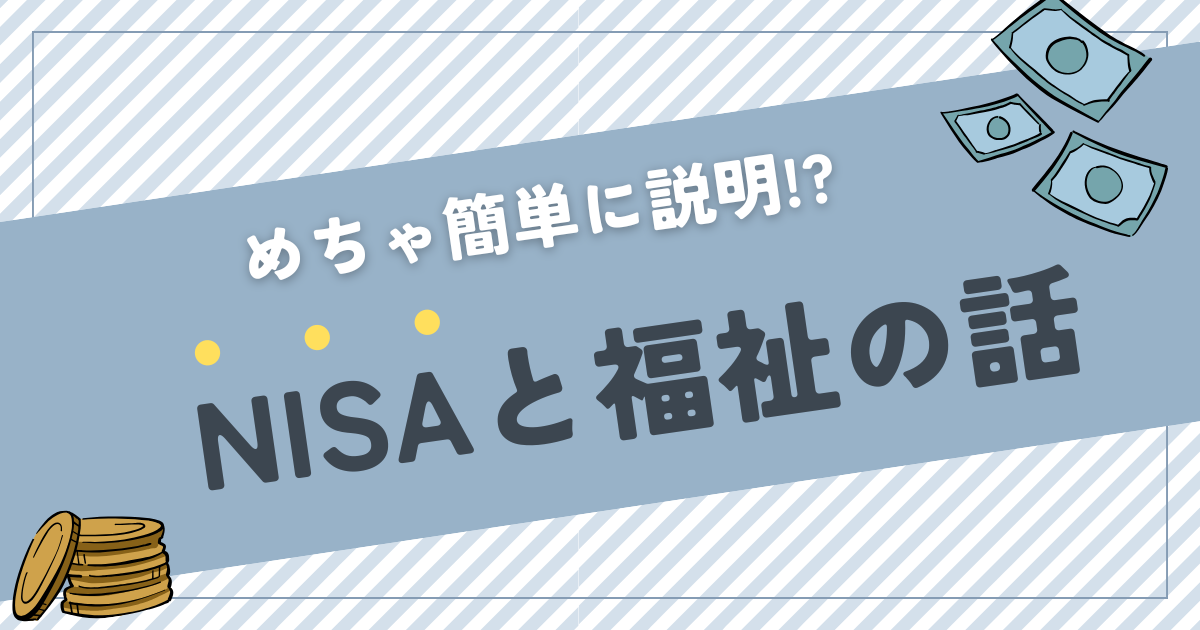
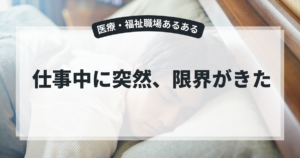



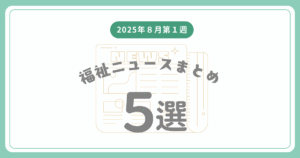
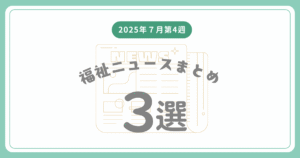
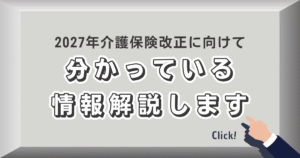
コメント