【現場の本音】介護・医療従事者いなさすぎて大問題。制度の限界と選挙の意味
こんにちは、晩酌福祉らじおです。
今回は、社会福祉士としての現場目線で「介護・医療の人材不足」という、超リアルな問題について語っていきます。
選挙シーズン、本格化
街を歩けば選挙カー、SNSでも候補者の名前がチラホラ。
いよいよ選挙本番という空気が漂ってきましたね。
そんな中で注目したいのが、福祉・医療系の政策。
一部の政党が、「介護職の待遇改善」「人材拡充」などを掲げていますが――
複数の政党が「人材確保」を強調している
たとえば最近よく見かける政策例は以下のとおり:
- 外国人介護士の受け入れ拡大
- 処遇改善(給料アップ)の強化
- 介護ロボットやICT導入支援
- 在宅介護への移行支援
- 医療・介護の連携強化
どれも一見「良さそう」な政策。でも、現場的にはツッコミどころ満載です。
外国人頼りでは根本解決にならない
外国人介護士の受け入れ。確かに人手は増えるかもしれないけど、現場ではこんな声が多いです。
- 日本語や専門用語が壁になる
- 利用者や家族とのコミュニケーションに難しさ
- せっかく育てても長期定着しない
正直なところ、「いないよりマシ」程度。
根本解決にはほど遠いのが現実です。
介護ロボットは補助にはなるが、完全代替は不可能
「ロボットが介護を変える!」と言われますが…
- 排泄介助や急変時対応、認知症ケアなどは人の判断力と感情の機微が必要
- 高齢者が機械に抵抗感を示すケースも多い
- メンテナンスやコストの問題も
補助的に使う分にはアリ。でも、それだけでは現場は回らない。
自宅介護、現実はもっと厳しい
「施設より在宅介護へ」という政策も増えてきていますが――
- 家族が介護にフルタイムで対応するのは現実的じゃない
- 医療や福祉サービスの支えがなければ、共倒れリスクが高い
理想だけでは介護は成立しないというのが、多くの現場の声です。
結局は「マンパワー」が必要
介護も医療も、人がいてこそ成り立つ仕事。
ロボットもICTも、あくまで「補助」。
最前線で支える人が足りない限り、どんな制度も崩れます。
給料を上げれば解決?制度上の限界もある
「人を集めるには給料アップだろ」と思いますよね。
でも、現行の介護保険・医療保険制度では簡単じゃないんです。
- サービス単価が国で決められていて、報酬に限界がある
- 財源がなければ処遇改善もできない
「じゃあ公務員にすればいい?」
それはそれで、昔の“措置制度”に戻るリスクがあり、
選べない介護・質の低下・給料横並びという問題も生まれかねません。
現場の答え:制度の抜本的改革が必要
現場で長年働いてきた身としての結論は一つ。
もう制度の根本を見直すしかない。
現状の枠組みの中で小手先の対応をしても、限界。
思い切って、福祉そのものの在り方を国レベルで見直す必要があります。
「自分には関係ない」では済まされない時代
福祉制度って、すぐには自分に関係なさそうに見えるけど――
- 親の介護が始まったとき
- 自分がケガや病気で支援が必要になったとき
- 子どもが発達障害など支援を受ける側になったとき
どこかで必ず関わる制度なんです。
選挙に行くことも「支えること」になる
だからこそ、政治や制度の話に「無関心」でいてはダメ。
選挙で「福祉をちゃんと考えてる人」に一票を投じる。
それが遠回りに見えて、現場を支える一番の力になります。
だからこそ、ちょっと砕けた発信をしています
おカタい話になりがちな福祉の世界。
だけど、それじゃ伝わらない。
だから私は晩酌しながらでも楽しめる、ちょっと砕けた福祉トークを発信しています。
「なんか気になる」
「ちょっと面白いかも」
そんな興味からでもOK。まずは知ってもらうことが大事なんです。
最後にひと言
というわけで、今日は介護・医療従事者不足のリアルと制度の限界について語ってみました。
ちょっと真面目な内容でしたが、
次回はまた、ゆる〜く晩酌しながら語りましょう。
ではまた、「晩酌福祉らじお」でお会いしましょう。かんぱ〜い!


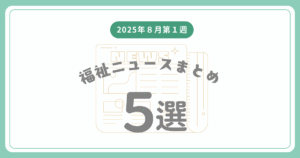
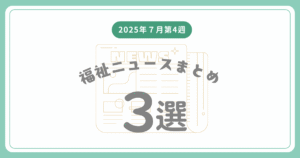
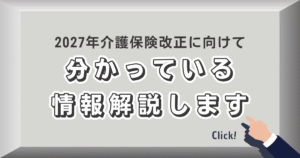
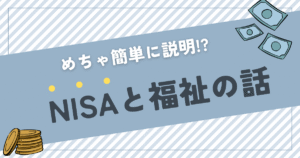
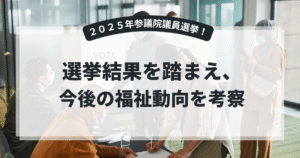
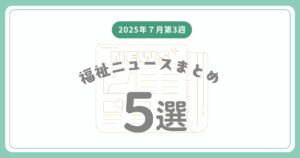
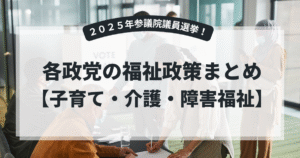
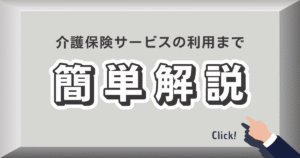
コメント